光合成の教科書を振り返る
その昔、指導教官であった加藤栄先生に「教科書を読まない園池君」と呼ばれていた筆者も、自分で講義をするようになると、さすがにいろいろ勉強するようになった。光合成の研究の歴史の古さを反映して、光合成に関する本も、古今東西さまざまなものが出版されている。その中で、比較的一般向けのものを中心に印象に残ったものをいくつか紹介してみたい。光合成研究会の方々には釈迦に説法であろうが、古い教科書の話をなつかしいと思ってくださる方もいらっしゃると思うので・・・

まずは、外国のものから三冊ほど。教科書として比較的有名なのはHallとRaoによる"Photosynthesis" (Camblidge University Press) だろうか。第6版が1999年に出版されていて、この時点までの最新の研究成果を取り入れた読みやすい本である。対象読者は学部生ぐらいだろうか。図版も多く、さまざまな観点からの光合成の話が盛り込まれている。古い版は金井龍二先生の訳で1980年に朝倉書店から出ているようであるが、こちらは実はまだ見ていない。その後、新しい版は出ていないようなのが残念である。
少し変わっているのがSF作家として有名なアイザック・アシモフによる"Photosynthesis" (Basic Books)。この人は、「銀河帝国の興亡」といったSFから、「黒後家蜘蛛の会」などのミステリ、そして科学解説書を山ほど書いた人であるが、ボストン医科大学の生化学の准教授でもあった。1968年に書かれたこの本は、エネルギーによって物質が循環するという側面から光合成を一般向けに解説したもので、おそらくは高校生ぐらいから読める素晴らしい本である。

一方、とてつもなく異色なのがWilbert Veit, Jr.という人の書いた"The Music of Sunlight" (Sunlight Books)という本である。2000年に出版された本で、内容は、光合成におけるトムキンスものといった感じである。ガモフの有名な物語では、良識あるトムキンス氏が奇妙な物理の世界に引き込まれていく中で相対性理論や量子力学が紹介されるが、本書では、しゃべる形容詞の8割が"cool"という男の子(中学生ぐらいか?)が、電子となって光合成の電子伝達の世界を経験するというものでGovindjeeやJohn Whitmarshの名前が助言者として載っている。主人公がシトクロムb6/f複合体上を通る際に、一度目はQサイクルによってプラストキノンプールに戻ってしまい、二度目にようやくプラストシアニンに行くというところなど、尋常ではないこだわりぶりが細部に見られる。英語は、口語的表現に慣れさえすれば平易であるが、一体このような本を誰が読むのか、という疑問は禁じ得ない。光合成のメカニズムを知らない人間にとってはさほど面白いとは思えないが、講義で光合成を習った大学生が、習ったことを記憶に残すために読むのであろうか。一応$19.95という定価がついているが、2001年のブリズベンの国際光合成会議の会場で希望者に無料配布されていた。やはり売れ残って処分に困ったのかも知れない。
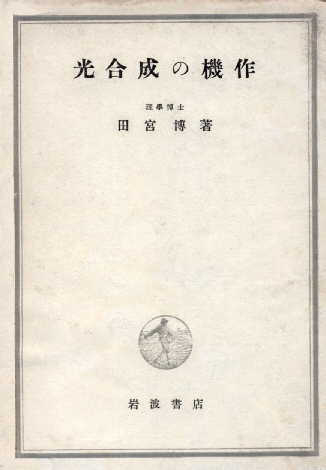
次に日本の本に移って、古いところから田宮博著「光合成の機作」。これは岩波書店から戦前の1943年に出た本で、内容よりもまずその文体が今となっては興味深い。「光合成は生物によって行なはれるものであるに違ひないが、自然科學者はこれを玄妙不可思議な「生命」現象として祭壇に祭り上げる必要は毛頭ない」、「然し吾々の解析が進むにつれて未知の事實は次々と現はれ、自然は愈々その技術の諜察を拒むが如く見える」といった調子である。内容的にも、ようやくHill反応が発見されたばかりでZスキームもカルビン回路もわかっていなかった時代の本である。記述されていることが、現在の何に対応するのかもよくわからない場合が少なくない。筆者の持っている本は、寺島一郎さんから14年ほど前に譲り受けたものであるが、正直に言うとまだ最初から最後までは読み通していない状態である。

同じ「光合成の機作」という題名の本が共立出版から藤茂宏先生などの編集で1979年に出ているが、こちらは当時の最先端の研究を網羅した和文総説集である。20のトピックが取り上げられており、今、そのトピックを見ると、村田紀夫先生による「クロロフィルの存在状態とクロロフィルフォーム」、山下魏先生による「トリス処理をめぐる諸問題」など、当時の研究の興味の方向性が思い出されてなつかしい。ちょうど筆者が大学院生のころに、高橋裕一郎さんなどの加藤研究室の大学院生に、当時研究室の助手だった佐藤和彦さんと山岸明彦さん、隣の村田研究室の宮尾光恵さん、東京理科大学の榎並勲さんも加えてこの本を輪講した。「序」として藤茂先生による「光合成研究の展開のあと」という文章が載っており、研究の歴史を1920年代のWarburgから説き起こす独特の文章に感心したものだった。

藤茂先生の本といえば、裳華房から1973年に出た「光合成」およびUP Biologyから1982年に出た「光合成」がある。前者は実は読んでいないのだが、後者は愛読した。その副題に「明反応研究の流れ」とあるように研究の歴史的展開を主軸にしていて面白い。上記の「光合成の機作」の「序」もそうであるが、「藤茂節」とでも呼びたい独特の調子が全編を貫いている。おもて表紙の見返しには光合成研究の「系統樹」が載せられていて楽しい。UP Biologyには西田晃二郎先生が1986年に「光合成の暗反応」を書いておられ、こちらは正統的で、発見の歴史的経緯を踏まえたわかりやすい教科書であった。
この他、単行本としては加藤栄先生の「光合成入門」(共立出版、1973年)が光合成全般を扱った教科書の中では良く項目が整理されており、極めて平易でわかりやすい。一方、これと対極にあるのが、西村光雄先生の「光合成」(岩波書店、1987年)で、その内容の詳細なことは他の教科書と比べても群を抜いているように思う。生物物理的な側面も比較的詳しく書き込んであり、学部学生には歯が立たないかも知れないが、研究室にリファレンスとして置いておきたい本であった。とは言え、最近Amazonで調べたら35,000円の値段がついていたので、今となってはおいそれとは買えないかも知れない。

次は朝倉書店の植物生理学講座のシリーズ。これは、皆さんおなじみだと思うので、特に内容には触れないが、2002年の最新シリーズでは「光合成」の巻だけでなく「環境応答」の巻でも光合成がかなり扱われている。学会などでも、昔は「光合成」というセッションだけ聞いていれば光合成関連の発表をある程度網羅できたが、最近は光合成の演題が様々なセッションに分散するようになっている。教科書でも同様の傾向があるのかも知れない。
上記の日本語教科書はいずれも読者の対象は大学院生か、せいぜい専門学部生以上であろう。そこで、大学1,2年生からすらすら読めることを目指して書かれたのが「光合成の科学」(東京大学出版会、2007年)である。東京大学の佐藤直樹さんが音頭を取って、駒場の先生を中心に「東京大学光合成教育研究会編」として出版された。筆者も著者の一人であるが、「学生が一人で読める教科書」としては成功したのではないかと思っている。

一方、一般向けの光合成の本となると、過去に唯一あったのが岩波洋造先生の「光合成の世界」(講談社ブルーバックス、1970年)である。40年近く前の本でありながら、一般向けの啓蒙書として読む限りにおいてはそれほど古い印象を与えない。著者が光合成の専門家ではないことがむしろ幸いしているのかも知れない。もし、専門家が当時わかりかけていた細かいメカニズムまで書き込んでいたら、おそらく、現在の目から見ると修正しなくてはならないことがたくさん出てきていただろう。岩波先生は写真を趣味にしていたそうで、光化学反応と酵素反応の温度依存性の違いを、写真の感光の反応と現像の反応にたとえて説明するところなどは、なるほどと感心させる。内容自体はかなり多岐にわたり、光合成を縦軸に、植物の生き方をさまざまに切り取っている。
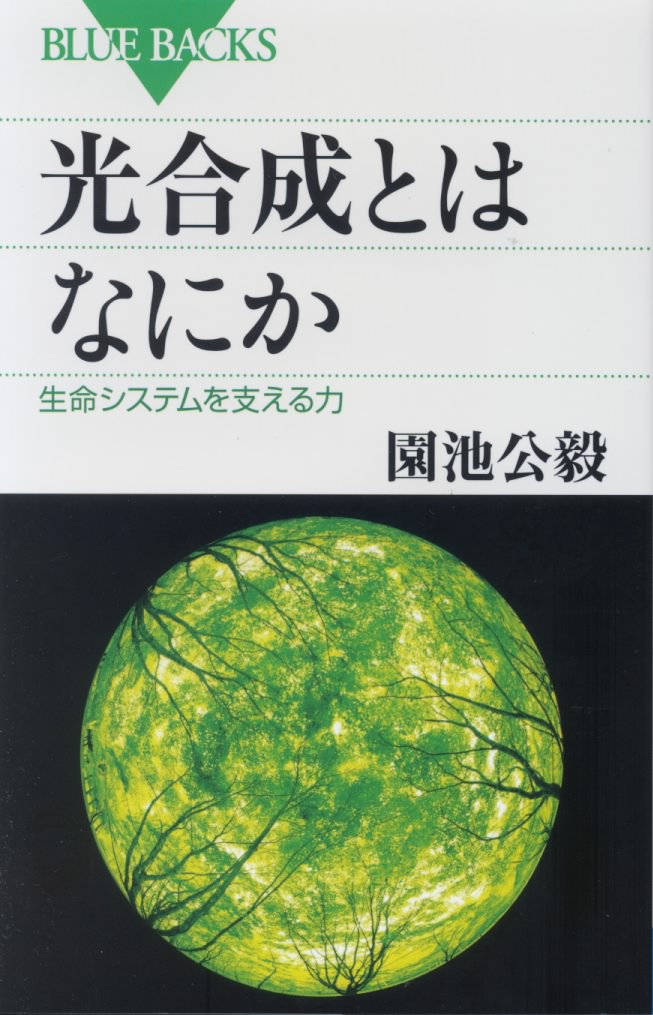
しかし、40年前の情報に基づいた本しかないというのは、いかんせん寂しいということで、今年、同じ講談社ブルーバックスから「光合成とはなにか」という本を出したので最後に少しばかり宣伝をさせて頂こうと思う。二年ほど前に寺島さんを通じてブルーバックス編集部から依頼があり、高校生でも読める文章で、かつ、教科書として基本的な事実は押さえること、というのが編集部からの要請であった。しかしながら、やはりこの二つの両立は難しく、結局、高校生にはやや難しい本に仕上がったかも知れない。ただ、内容的にはその分、かなり書き込んだので、学部の講義に使ってもよいような内容となっている。千円札でお釣りが来る本なので、一度ご覧頂ければ幸いである。
以上は、2008年に光合成研究者向けに書いたもので、これの短縮版が光合成研究会(現在の光合成学会)が出版している「光合成研究」に掲載された。